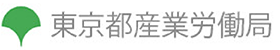税優遇の内容
税優遇の内容
個人投資家は株式取得時点、株式売却時点のそれぞれの時点において、税制上の優遇措置を受けることができます。
優遇措置を受けるためには、基準日において企業要件と個人投資家要件をすべてみたす必要があります。
| 株式取得時点 | 優遇措置A | 優遇措置 B | プレシード・シード特例 | |
| 対象となる投資先 | 設立5年未満の企業 | 設立10年未満の企業 | 設立5年未満の企業 | |
| 控除対象 |
寄付金控除の適用 「対象企業への投資額ー2,000円」 をその年の総所得金額等から控除 (注1)
|
対象企業への投資額全額を その年の他の株式等譲渡益から控除 (注2)
|
対象企業への投資額全額を その年の他の株式等譲渡益から控除 (注2)
|
|
| 控除上限額 |
総所得金額等 × 40%と 800万円のいずれか低い方 |
上限なし
申告分離課税のうち
所得税の15%が優遇措置の対象 (住民税の5%は対象外) |
上限なし
申告分離課税のうち
所得税の15%が優遇措置の対象 (住民税の5%は対象外) |
|
|
注1 総所得金額等とは、所得税法上の総所得金額(申告分離課税の対象となる株式等譲渡益等を含む)のことであり、退職所得金額と山林所得金額を含みます。
基準日が令和2年12月31日以前の場合は上限額が異なります。
注2 他の株式等譲渡益には未上場株式だけでなく上場株式等も含まれます。 |
||||
| 株式売却時点 | 優遇措置の内容 | 課税の繰延 | 課税の繰延 | 非課税 |
| 譲渡損失(譲渡益)の算定 | 取得価額の調整あり | 取得価額の調整あり |
投資額20億円まで 取得価額の調整なし それを超える分は課税の繰延 |
|
| 【取得価額の調整とは】株式取得時の優遇措置を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて株式譲渡益を算定します。 | ||||

|

|

|
||
|
譲渡損失
発生
その年の他の株式等譲渡益と通算(相殺)
※翌年以降3年にわたり通算可能 ※破産、解散等した場合も可能
譲渡益
発生
譲渡益に応じて課税
|
||||
| ※ | 基準日が令和5年3月31日以前の場合はプレシード・シード特例の適用はありません。また、基準日が令和2年3月31日以前の場合は対象となる投資先の企業要件が異なります。 |
税優遇が受けられなくなる場合
次の場合、「全ての個人投資家」はエンジェル税制の優遇措置を受けられませんので、ご留意ください。
新設合併 新設分割 純粋持株会社 有限責任事業組合(LLP)経由の投資 外国法人
次の場合、「該当する個人投資家のみ」がエンジェル税制の優遇措置を受けられませんので、ご留意ください。
課税の繰延べ
株式取得時の優遇措置(優遇措置Aまたは優遇措置B)の適用を受けた場合には、その適用を受けた株式の取得価額について一定の調整計算(取得価額の調整)が必要となります。
【取得価額の調整とは】売却時の優遇措置を受ける場合に、他の株式譲渡益と相殺できる損失金額を計算する際に、当該株式の取得価額から優遇措置の適用を受けた金額を差し引く調整を行うことです。
【取得価額の調整が必要ない場合】
株式取得時にプレシード・シード特例の適用を受けた場合において、その適用を受けた金額が20億円以下であるときは、取得価額の調整が不要です。※適用を受けた金額が20億円を越える場合には、その超えた部分については取得価額の調整が必要となります。
【確定申告の際の留意事項】
取得価額の調整は所得税(国税)のみが対象です。住民税(地方税)は株式取得時の優遇措置の対象ではないため、売却時点での取得価額の調整は行われません。*譲渡損失(譲渡益)の算定方法*
所得税の場合:譲渡価額ー取得費(原始取得価額ー優遇の適用を受けた金額)
住民税の場合:譲渡価額ー取得費(原始取得価額)
<個人投資家が行う住民税への対応>
現行の制度では、過去にエンジェル税制を利用した株式であろうとなかろうと税務署と同様の算定方法で、本来の取得費ではない取得費で住民税の譲渡損益が計算される可能性があります。そこで、つぎのどちらかの対応をすることをお勧めします。
▶エンジェル税制を利用した際の確定申告書類に添付した明細書の控えを任意添付書類として添付し、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の「④取得費(取得価額)」の欄に付箋等で、「過去にエンジェル税制を利用し、調整を行った取得費」等の記載を行ったうえで税務署に確定申告を行う。
▶住民税を管轄する区役所や市役所の担当者に直接説明をする。